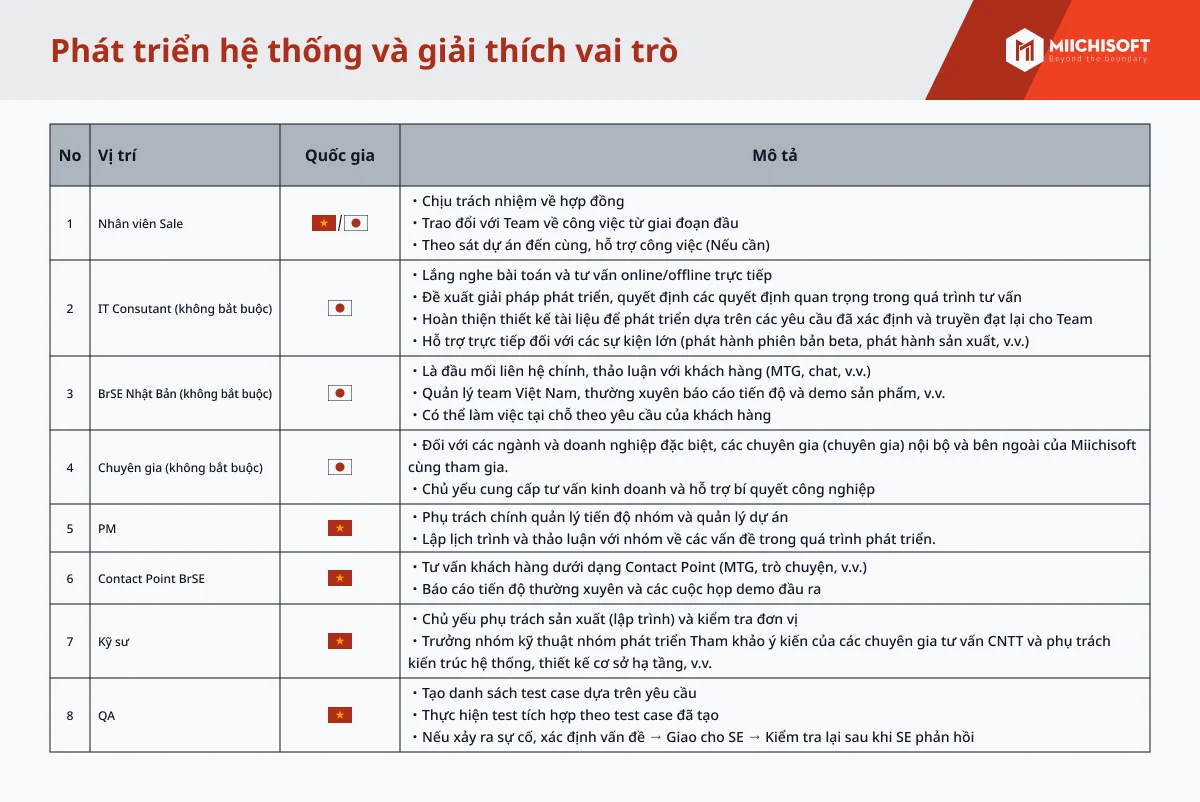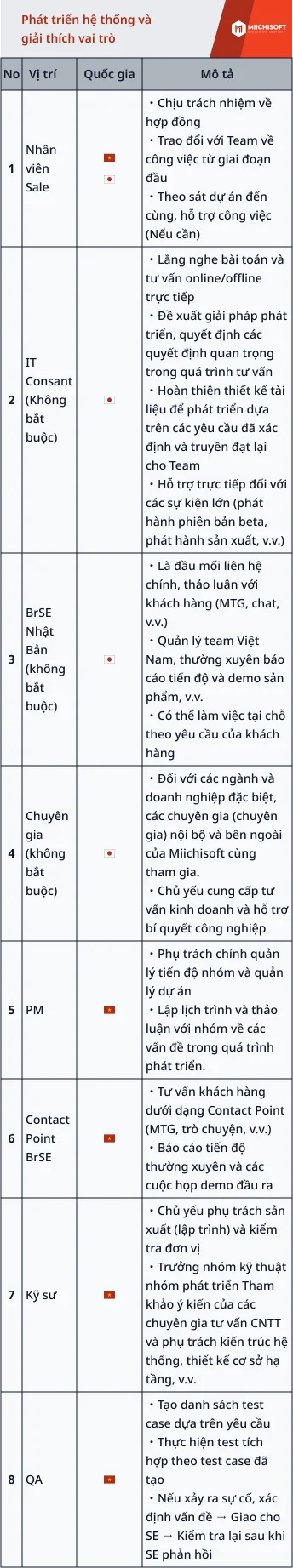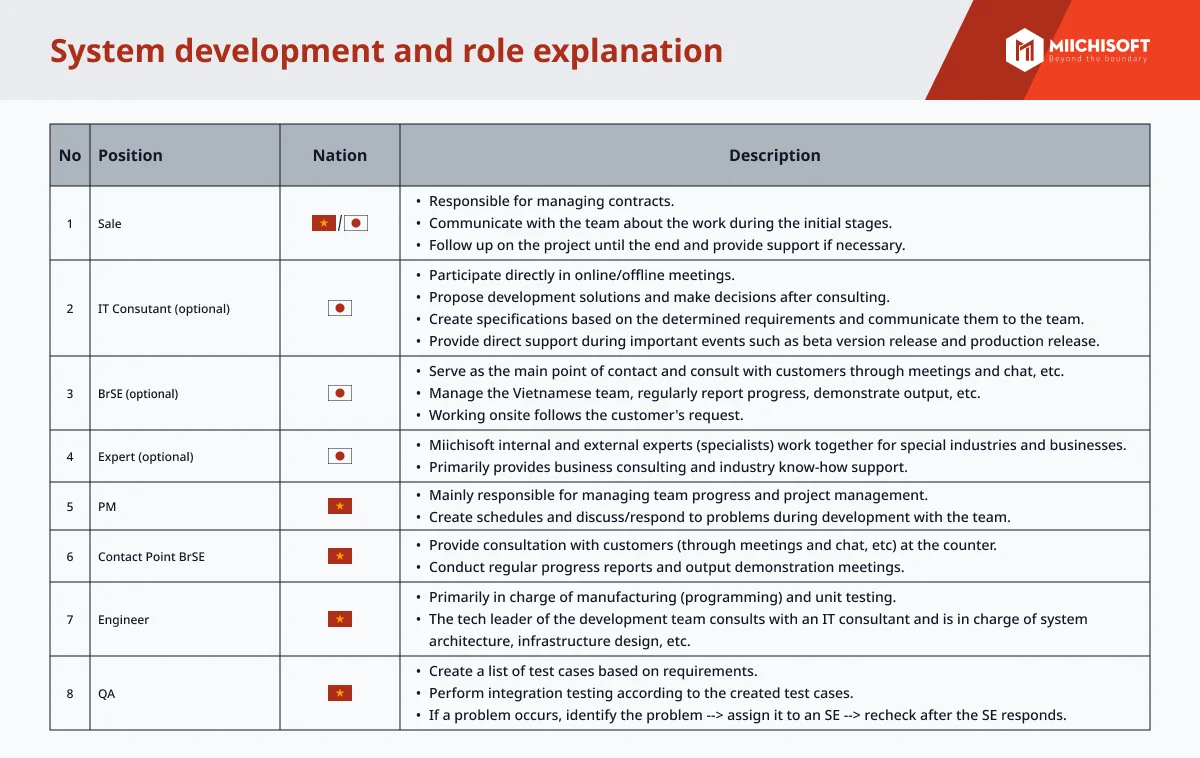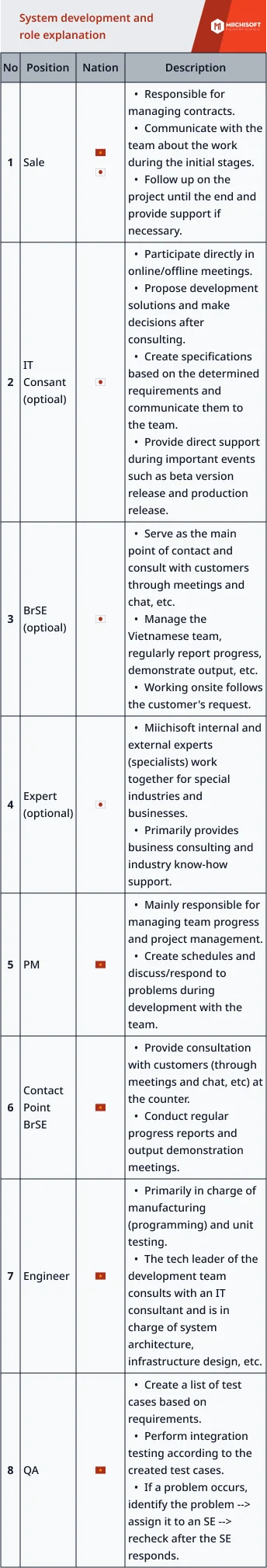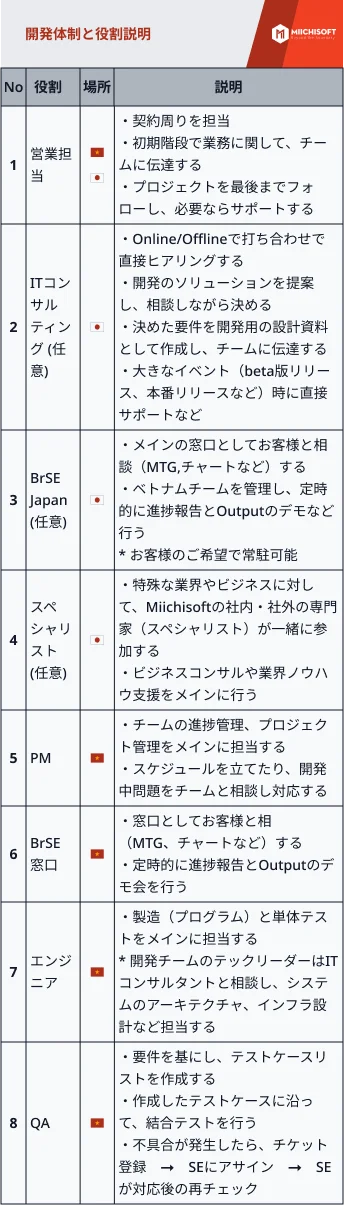経済産業省(METI)の報告によれば、2030年までに日本では最大79万人のITエンジニアが不足すると予測されています。DX推進が加速する中で、この数字は企業にとって大きなリスクとなり得ます。
そのような状況下、AIローコードプラットフォームは新しい解決策として注目を集めています。従来よりも効率的にシステムを開発し、IT予算を最適化できる可能性があるからです。
しかし、本当にAIローコードプラットフォームを導入すればIT人材採用コスト削減が実現できるのでしょうか? 本記事ではその疑問に迫りつつ、運用前に企業が確認すべき4つのポイントを解説します。
1. AIローコードプラットフォームとは? IT人材採用コスト削減につながる仕組み
1.1 AIローコードプラットフォームとは?
AIローコードプラットフォームとは、AIを統合したローコード開発プラットフォームのことを指します。プログラミング知識がなくても、直感的なUIやドラッグ&ドロップ操作でアプリケーションを開発できるのが特徴です。AIや機械学習を組み合わせることで、データ処理の自動化、意思決定の支援、そしてスマートな業務プロセスの構築が可能になります。
現在では、n8n、Dify AI、MakeといったAIローコードプラットフォームが広く利用されており、社内情報検索、コンテンツ生成、スケジュール作成など、各部門が多様な業務を効率化するために活用されています。最大の強みは、インテリジェントなワークフローを構築できる点であり、これにより業務プロセスがスムーズになり、手作業によるミスを大幅に削減できます。その結果、企業にとってはIT人材採用コスト削減への期待が高まっています。
参考記事: AI搭載ローコードプラットフォーム5選|スピードと柔軟性で企業DXを加速
1.2 AIローコードプラットフォームはどのようにIT人材採用コスト削減につながるのか
1.2.1 少人数体制でも開発スピードを加速できる理由
ソフトウェア開発において、ITチームの業務は大きく「反復的な作業」と「複雑なカスタマイズ作業」に分かれます。機能設計やパフォーマンス最適化、業務プロセス特化の処理などのカスタマイズ作業はシステムに高い価値をもたらします。一方で、基本モジュールの構築、API統合、手動テストといった反復作業は、プロジェクトリソースの40〜60%を占めながらも付加価値は低いのが実情です。
AIローコードプラットフォームは以下のような方法でIT人材採用コスト削減に貢献します。
・反復的な機能を自動化:標準モジュールのコード生成により、プロジェクトの40〜60%を占める作業時間を大幅に短縮。
・迅速な統合:既存のテンプレートライブラリを活用することで、ゼロから開発する場合に比べて大幅に効率化。
・ITエンジニアのAIアシスタント:コードの提案・補完・完成を支援し、エンジニアは業務ロジックに集中可能。
・フィードバックサイクルの短縮:直感的なUIにより業務部門とITの連携が円滑になり、要件の誤解や遅延を防止。
・自動テスト・自動デプロイの統合:エラーの早期発見と手作業によるミスの抑制を実現。
これにより、同じ業務量でも少人数体制でプロジェクトを進められ、開発スピードを維持しながら人件費を抑制することが可能になります。

小林製薬は、日本の老舗製薬企業として長い歴史を持ちながらも、デジタル化の過程で多くの課題に直面してきました。従来はソフトウェア開発を外部委託しており、新しいアプリケーションを完成させるまで平均6か月を要していました。この方法はコスト増大を招くだけでなく、DX推進のスピードを大幅に遅らせる要因となっていました。
こうした業界の変化への対応を迫られる中、小林製薬はAIローコードプラットフォーム「OutSystems」を導入しました。ドラッグ&ドロップ操作や既存モジュールを活用できる仕組みにより、新機能のリリース期間をわずか数日〜数週間に短縮。
これにより、社内ITチームは400本に及ぶWebアプリケーションのモダナイゼーションを迅速に進めると同時に、戦略的なR&D活動へリソースを集中できるようになりました。AIローコードは、同社のDXを加速させる大きな原動力となっています。
1.2.2 既存人材を活用し、IT部門をスリム化する
AIローコードプラットフォームを導入することで、人事、マーケティング、オペレーションなどの各部門が自ら業務を支援するITソリューションを設計できるようになります。これにより部門間の連携が強化されるだけでなく、社内IT部門の負担も軽減され、結果としてIT人材採用コスト削減や組織のスリム化につながります。その結果、コアエンジニアは高度な技術を要するプロジェクトに専念することが可能になります。

実際に、ドイツのフードデリバリー大手 Delivery Hero はAIローコードプラットフォームを活用して課題を解決しました。同社では従業員の異動、休暇、退職に伴い、システムアカウントのロック、再開、アクセス権の復旧が頻発。従来はIT部門が複数のシステムで手作業を行う必要があり、1アカウントあたり平均35分を要していました。
しかし、AIローコードプラットフォーム n8n を導入し、Okta、Jira、Google Workspaceといったシステムに自動APIコールを行うワークフローを構築したことで、この復旧作業は20分に短縮。月間200時間以上の工数削減を実現しました。その結果、社員のリクエスト対応が迅速化し、従業員体験が向上するとともに、ITチームの規模と生産性も最適化されています。
参考記事:企業が毎月数千時間の無駄を防ぐには?業務プロセスへのAI導入・3つのステップ
2. AIローコードプラットフォームでIT人材採用コストを完全に削減できるのか? 運用前に知るべき4つの注意点
AIローコードプラットフォームは、企業におけるIT人材採用コスト削減やアプリ開発の加速、業務運用のスリム化に大きく貢献してきました。とはいえ、完全にIT人材コストをゼロにできるわけではありません。なぜなら、AIローコードだけでは高度で複雑なシステム開発ニーズに対応しきれないからです。ここでは、導入前に押さえておくべき4つの注意点を紹介します。
2.1 複雑なプロジェクトには専門的な開発チームが不可欠
AIローコードが最も効果を発揮するのは、アイデアを素早く形にしたい場合や、データの取得、小規模な部門単位のプロセス自動化といったシンプルなアプリ開発です。しかし、ERP、サプライチェーン管理、大規模ECサイトのようなコアシステムの開発になると、その複雑さはAIローコードの範囲を超えます。
このようなケースでは、プロフェッショナルなITチームが必要です。
・システムアーキテクチャ設計:AIローコードプラットフォームは試作品を迅速に作成できますが、実際の企業運用環境では、データ構造、ユーザー権限設計、セキュリティを含めた体系的な設計が欠かせません。ITチームは業務プロセスとの適合性や将来的な拡張性を担保します。
・特化機能の開発:業界ごとに必要な特殊機能はAIローコードプラットフォームに標準搭載されていない場合が多いため、専門的な開発力が不可欠です。
要するに、AIローコードは小規模でシンプルなアプリ開発をスピーディーに実現する強力な手段ですが、企業全体の基幹システムを構築・運用するためには、依然としてプロのITチームが重要な役割を担います。
2.2 AIローコードプラットフォーム導入時のセキュリティ課題
現在多くのAIローコードプラットフォームは、SaaSまたはクラウドサービスとして提供されています。これはつまり、企業の業務データが第三者のインフラを経由することを意味し、情報セキュリティへの懸念を引き起こします。特に日本では、法規制遵守やデータ保護に対するプレッシャーが高まっているため、このリスクは無視できません。
企業がIT人材採用コスト削減を目的としてAIローコードプラットフォームを長期的に導入・運用する場合、プラットフォームのセキュリティ確保に関する知識を十分に持つことが不可欠です。そのためには、データガバナンスの枠組みを整備し、明確なセキュリティプロセスを策定し、さらに継続的なモニタリングを実施する必要があります。
これらの対応を怠れば、コスト削減や導入スピードといった利点は大幅に制限され、最悪の場合、情報セキュリティリスクによって企業に新たな負担をもたらす恐れがあります。
2.3 AIローコードラットフォームではソフトウェアの安定性を完全に保証できない
AIローコードプラットフォームはアプリ開発のスピードを大幅に短縮できる一方、その処理範囲はあくまで基本的なレベルにとどまります。ERPやCRMといった基幹システムを導入する際には、単にIT人材採用コスト削減を優先するのではなく、ソフトウェアの安定性を確保するために専門的なIT人材を配置する必要があります。
以下の表は、「運用の安定性」という観点から、AIローコードと経験豊富なIT人材の違いを示したものです。
| 評価基準 | AIローコード | 経験豊富なIT人材 |
| コードのレビュー・最適化 | 自動コード生成は速いが、冗長部分の制御が弱く、大規模データ時に性能低下の可能性あり。 | コードを分析・修正し、不要部分を削除して高いパフォーマンスを維持。 |
| 複雑なシステム統合の対応 | 既存APIを通じた基本的な接続は可能だが、特殊な統合や基幹システムには制限あり。 | 複雑な統合を設計・実装し、データの同期、安全性、業務の継続性を確保。 |
| 拡張性・保守性 | プラットフォームの制約が強く、急な要件変更には対応が難しい。 | 柔軟なアーキテクチャを構築し、容易な拡張と長期的な保守コストの低減を実現。 |
2.4 AIローコード導入拡大に伴う「隠れたコスト」のリスク
AIローコードプラットフォームは、初期導入コストを最適化できるソリューションとして紹介されることが多いです。しかし、長期的に運用する中で、企業は以下のような隠れたコストに直面する可能性があります。
・ライセンス費用:多くのAIローコードプラットフォーム基盤はサブスクリプション型で提供されています。ユーザー数やアプリ数が増えるにつれ、ライセンス費用は当初の見積もりを大きく上回ることがあります。
・システム統合コスト:基盤がERP・CRM・コアバンキングなどの基幹システムと完全に互換しない場合、追加の技術者やミドルウェアが必要となり、コストが発生します。
・維持・アップグレード費用:ベンダー依存度が高いため、機能変更やポリシー改訂、バージョンアップに伴い、安定稼働を維持するための追加費用が求められるケースがあります。
・移行コスト:長期的な要件に対応できない場合、データやプロセスを新システムに移行する必要があり、多大な人員リソースと時間を消費します。
経営の視点から見ると、AIローコードプラットフォームは短期的にIT人材採用コスト削減を支援します。 しかし、長期的には総所有コスト(TCO: Total Cost of Ownership)こそが意思決定の重要な指標となります。したがって、目先のコスト削減だけでなく、AIローコードプラットフォームを導入する際には「コスト・リスク・拡張性」を含めた全体戦略の中で評価することが不可欠です。
3. ITエンジニアを採用すべきか、AIローコードプラットフォームを活用すべきか? 中小企業の最適解は?
AIローコードプラットフォームは、専門ITエンジニアを完全に代替することはできません。
したがって、企業は状況に応じて両者を柔軟に選択し、デジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させながら投資コストを最適化する必要があります。
以下は、中小企業が判断する際の簡単なガイドラインです。
| 企業の状況 | 適したソリューション | 主な理由 |
| 新製品を迅速に試作・検証したい | AIローコードプラットフォーム | アイデアをすぐに形にし、短期的にIT人材採用コスト削減を実現 |
| 業務効率を自動化ワークフローで改善したい | AIローコードプラットフォーム | 高度なカスタマイズ不要、非エンジニア人材も参加可能 |
| 長期的に基幹システム(ERP/CRMなど)を構築したい | ITエンジニア | 柔軟性・拡張性・長期的最適化を担保 |
| セキュリティ・法規制遵守が必須の案件 | ITエンジニア | アーキテクチャ設計やデータ保護を主体的に管理 |
| 限られた予算でIT人材不足に直面 | AIローコードプラットフォーム | 短期的にIT人材採用コスト削減を可能にし、スリムな組織を維持 |
| 技術的な主導権を保持したい | ITエンジニア | プラットフォーム依存リスクを回避 |
さらに、開発スピードとセキュリティ・技術要件を両立させるためには、AIを活用したソフトウェア開発に経験豊富なITチームが不可欠です。AIのサポートにより、ソフトウェアエンジニアは人員を増やさずとも多くの業務を処理でき、IT部門を常にスリムに保ちながらパフォーマンスを継続的に管理・測定することが可能になります。
4. ソリューション紹介:Miichisoftの「Core Labo AI+」
Core Labo AI+は、Miichisoftが提供する「AIを活用したソフトウェア開発に経験豊富なIT人材モデル」です。このモデルは次の2つの要素によって構成されています:
・Core Labo: 中長期的に企業を支える高い専門性を持つエンジニアチームを提供。
・AI+:CursorやChatGPTなど先端AIツールを活用できるIT人材が、要件分析・設計・開発をスピーディに実施。
これにより、企業は AI を活用した コスト削減と開発スピードの向上 を実現しつつ、熟練エンジニアによる 品質保証・セキュリティ・長期的拡張性 を同時に確保することが可能です。
Miichisoft の強みは、7 年以上の経験 と 200 件以上の成功プロジェクト(日本、シンガポール、香港、ベトナム)に裏付けられています。私たちは、企業のDXを加速させ、持続的かつ安全なシステム構築を実現する信頼できるパートナーとして伴走いたします。
5. 結論
AIローコードは、プログラミング知識がなくてもアプリケーションを迅速に開発できる可能性を切り開きました。しかし、それはソフトウェアエンジニアを完全に代替し、長期的に IT人材採用コスト削減 を実現できるという意味ではありません。複雑なシステム、厳格なセキュリティ、将来的な拡張を求める場合には、専門性の高いエンジニアチームこそが長期的に最適な投資となります。
「AI か IT か」という二者択一ではなく、両者を賢く組み合わせることが重要です。これは、Miichisoft が提供する Core Labo AI+ によって実現できる価値でもあります。このモデルを活用することで、企業は AI の持つスピードとコストメリットを享受しながら、エンジニアによる品質・セキュリティ・持続性の保証を得ることができます。
AI と IT を正しく組み合わせることは、DX を加速させ、IT人材採用コスト削減 を実現し、将来にわたって持続可能なシステム構築を可能にする「賢いレバレッジ」となるのです。
FAQ
Q1:中小企業はAIローコードから始めるべきか、それともIT人材チームを構築すべきか?
A:中小企業にとって、AIローコードは初期導入の合理的な選択肢となります。理由は「IT人材の採用コスト削減」と「MVPや社内アプリの素早い検証」が可能だからです。ただし、選択の基準は企業規模だけではありません。プロジェクトの目標や複雑性によって異なります。高度なカスタマイズ、厳格なセキュリティ対策、基幹システムとの統合が必要な場合は、経験豊富なエンジニアの協力やハイブリッド型の体制構築が不可欠です。そうすることで、長期的な拡張性と品質を確保できます。
Q2:AIローコードでIT人材コストを削減すると、製品の品質に影響しますか?
A:完全にAIローコードに依存すると品質に影響が出る可能性はあります。AIローコードはスピードとコスト面で強みを発揮しますが、コードの最適化やセキュリティ強化には熟練したエンジニアのチェックが必要です。両者を組み合わせることで「コスト削減」と「高品質な開発」を同時に実現できます。
Q3:AIローコードで開発したソリューションのセキュリティはどのように保証されますか?
A:現在、多くのAIローコードプラットフォームは複数のセキュリティ層を導入しています。具体的には、企業内でのデータ保管、アクセス権限管理、国際的なセキュリティ基準(例:GDPR、ISO27001)への準拠などです。これにより、企業はAIの力を活用しつつ、基幹システムの安全性を維持することができます。Miichisoftではさらに強固な体制を採用しており、データは顧客のインフラ上(ローカライズ環境)に直接展開可能であり、外部AI学習に利用されることは一切ありません。また、全システムがGDPRやISO27001に準拠しているため、短期的にも長期的にも安心してAIローコードを導入できます。
Q4:AIに精通したIT人材はどこで採用すべきですか?
A:企業はGitHubやLinkedIn、AIコミュニティ、ハッカソン、フリーランスプラットフォームなど、多様なチャネルを通じてAI人材を探すことができます。しかし、GitHub Copilot、Tabnine、Replitといったツールを実務レベルで使いこなせる人材を見極めるには、多大な時間とリソースを要します。その点、Miichisoftの Core Labo AI+ モデルを活用すれば、すでにAI活用に熟達したエンジニアチームが即戦力としてプロジェクトに参画でき、採用や育成の負担を大幅に削減できます。
Q5:AIを活用するITエンジニアを採用する場合、従来型のITチームに比べてどのようにコストを削減できますか?
A:コスト削減は、プロジェクト全体の費用と中長期的な運用コストに大きく反映されます。
例としてプログラミング作業を比較すると:
・従来型ITエンジニア:コードをすべて手作業で記述し、多くのテスト時間が必要。バグ発生率も高く、その分人件費や修正コストが膨らみやすい。
・AI活用エンジニア:AIを使ってコードを自動生成・提案させ、バグ検出やテストケース自動生成を効率化。開発スピードが向上し、作業量が減るためチームをスリム化できる。
その結果、プロジェクトは短期間で完了し、IT人材コストを長期的に抑えると同時に、保守・運用コストの追加削減にもつながります。